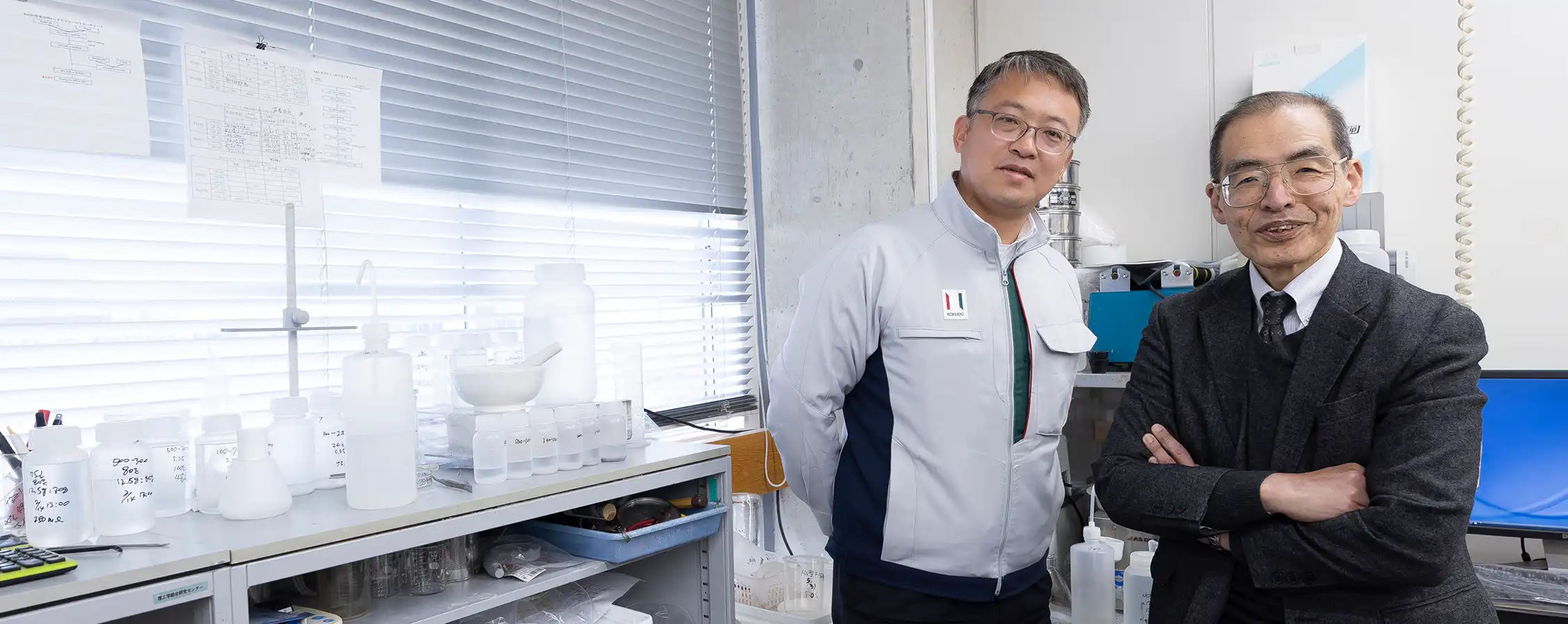環境資源工学
前編
「地球物質」を、どう活かすか
「地球物質」と、どう生きるか
金属やコンクリートといった、様々な素材を使用する建設。その素材も、元を辿ればすべて地下に埋まっている資源鉱物から作られています。今回取り上げるのは、そんな資源鉱物を扱う「環境資源工学」です。早稲田大学 理工学術院の山﨑教授に、環境資源工学と土木のつながり、社会課題の解決に向けた取り組みについて話を聞きました。

山﨑淳司
早稲田大学 理工学術院教授。同大学の教育学部 理学科地学専修を卒業後、大学院から理工学研究科 資源工学分野へ。現在は、まだ活用の仕方が見つかっていない鉱物資源を原料とした高機能素材の開発など、応用研究に取り組む。専門分野は環境資源工学。

劉兆涛
日本国土開発 つくば未来センター 化学グループ。出身国である中国で建築を学び、建設会社での勤務を経て、来日。中央大学で土木工学のコンクリート分野を専攻した後、日本国土開発に入社し、水中のヒ素を除去する機能性材料の開発などに携わる。
地中に眠る、可能性の宝庫
建物を建てる、インフラをつくる。建設のそうした仕事を支えるのは、地球から生み出された無数の資源。土木・建築はもとより、ありとあらゆる産業と密接な関係にある「環境資源工学」とは、どのような学問なのでしょうか。
- 山﨑:
- 私は「地球上にあるもの、すなわち地球物質はすべて資源である」と言っているんですよ。低付加価値とされる物質も有効な活用方法が見つかっていないだけで、実は社会課題を解決できるポテンシャルを秘めているかもしれない。そうした資源鉱物を見つけてきて人間のために役立てていこうというのが、私たちの研究している環境資源工学です。

- 劉:
- 資源鉱物といっても一般の方にはピンと来ないかもしれません。でも私たち建設会社が使うコンクリートや鉄はもちろんのこと、生活の中にあふれるプラスチックやガラス、それに電池なども、もとを辿れば鉱物からできています。私たちの社会は、資源鉱物なくして成り立たないですよね。
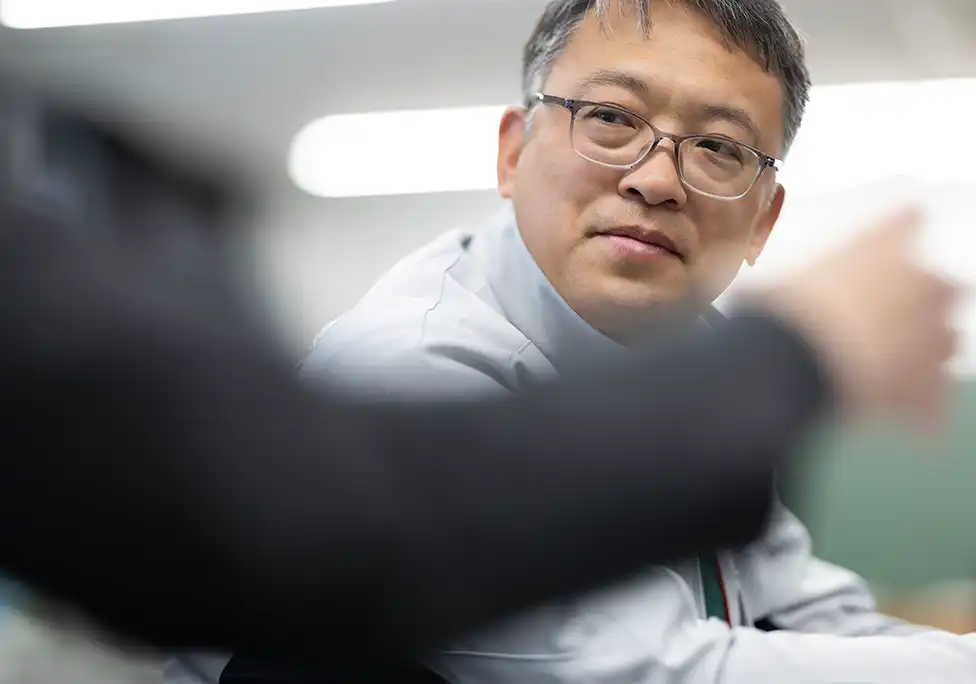
- 山﨑:
- そうですね。建設と環境資源工学は、非常に近い立ち位置にあります。社会にとって必要不可欠なものを取り扱っているという点でも、それから、日常生活ではなかなか存在を意識されないという点でも(笑)。早稲田大学に関して言えば、そもそものルーツは大隈重信が開校当初に設立し、発展した「鉱山学科」なんです。
- 劉:
- 「鉱山」は土木との関係も深いですよね。どちらも地面の下を扱うものですから。
- 山﨑:
- 京都大学など、学科・専攻として「資源」と「土木」が一体になっているところも多いですね。資源工学には、どこに何が埋まっているかという「探鉱」とか、余分なものを取り除いて精製する「選鉱」というプロセスがあり、これらが発達する中で、地盤や土砂の状態を調べる技術も生まれてきました。そんなところからも、建設の技術発展に貢献できている学問なのではないかなと思っています。
環境資源工学が立ち向かう課題
私たちの文明を支える無数の素材と構造物。その裏側には、資源の探査、採掘、精製から生産、使用、そして廃棄までの長い道のりがあります。この過程で生じる環境負荷をいかに減らし、限られた資源を循環させていくか——現代社会が直面する最も重要な課題の一つです。

- 山﨑:
- 現在の私たちの重要課題は、人間社会の「持続可能性」に関するものです。地球から得られた資源を用いて人間の生活を豊かにするのはもちろん、これをいかに循環型のものへとシフトしていくかということですね。劉さんがかつて研究されていたコンクリートに関するものでは、原材料となるセメントをつくるときのCO2をどう減らすかも課題になっていますね。そして、使用後のコンクリートをどう再利用するかということも。
- 劉:
- ええ。コンクリートの製造段階では、まずセメントクリンカという石灰と石膏、硫酸カルシウムから「セメントペースト」をつくります。このとき、石灰を高温で「焼く」必要があり、CO2が多く発生するのですね。石灰石の主成分は炭酸カルシウムです。これを焼くので当然炭酸ガス、つまりCO2が発生してしまうわけです。
- 山﨑:
- これを、火力発電所から発生する「フライアッシュ」や、製鉄所から発生する「スラグ」と呼ばれる産業副産物に置き換えれば、石灰石由来のCO2を削減できます。世界の産業全体から排出されるCO2のうち、約7%がコンクリートの製造段階のものといわれていますので、これを削減するのは重要な課題だと言えますね。

- 劉:
- あと、コンクリートは「ペースト」のままでは十分な強度が出ません。砂利などの「骨材」を混ぜる必要があるのですが、ここにも使用済みのコンクリートを破砕・処理した「再生骨材」を用いれば、天然資源の使用量を減らせます。ただ、材料としての再生骨材も注意深く扱わないと、アルカリ骨材反応といって、コンクリートの劣化を促進させることにもなり得ます。
コンクリート構造物の劣化も大きな社会問題になっていますよね。コンクリートのひび割れから水や空気が侵入することで鉄筋が膨張し、コンクリートが内部から破壊される──「塩害」が代表例ですが。
- 山﨑:
- そうですね。道路や橋、下水道などコンクリートからつくった社会インフラをどのように維持していくか。適切に補修を行うことが重要ですが、ほかにも素材の面から解決を試みる方法もあります。たとえば、材料にアルカリを用いる「ジオポリマーコンクリート」などですね。
- 劉:
- 通常のコンクリートに含まれるセメント中のカルシウム、つまり石灰に代えてアルカリを用いるものですよね。
- 山﨑:
- 通常のコンクリートの場合は結晶が組み合わさったものであるのに対して、こちらは結晶構造を持たない「アモルファス」の状態で固まった「ポリマー」という性質をとります。言ってみればプラスチックに近いんですね。非常に安定しているのが特徴で、ローマのコロッセウムに用いられた「ローマンセメント」に近い性質を持っています。そう考えると、少なくとも2,000年は保つわけで、インフラの長寿命化という意味で非常に効果的だろうといわれていますね。資源鉱物の使い方によって、こうした材料を生み出すこともできるわけです。
実験室から現場へ──
「社会実装」への挑戦
優れた技術が実験室から社会へと広がるためには、乗り越えるべき壁があります。そのひとつが「コスト」。科学的な発見から実用化へとつなげるために、必要とされるエンジニアリングの力とは。
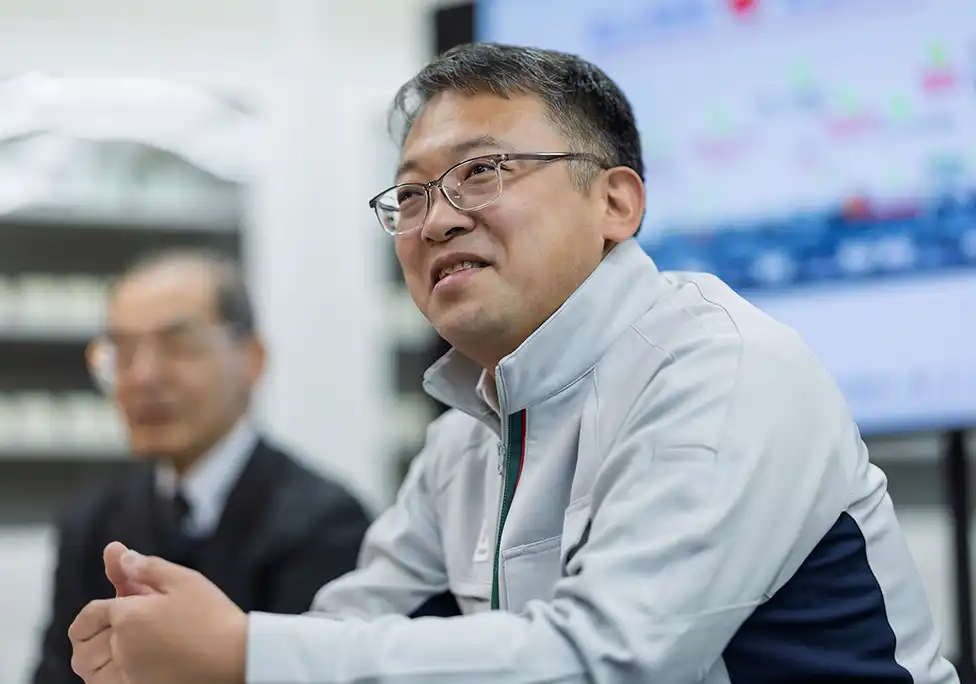
- 劉:
- さきほど挙がったジオポリマーコンクリートの例では、石灰の代わりに用いられる水酸化ナトリウムが非常に高価ですね。海水からつくる方法がいちばん手っ取り早いと思いますが、それでも相当高く付きます。「では明日から使いましょう!」というわけにはいかないですね。
- 山﨑:
- 安定して量産ができるレシピが確立されていないというものもありますが、最も大きな要因は、建設用の原材料として使うには「コストに見合わない」という点です。新しい素材は技術的に「これだ」というものがあったとしても、実際に社会で利用できるようになるのは、100個のうち数個あるかないか、といったところですね。

- 劉:
- どんなにいいものでも、従来の材料と同等程度のコストに抑えられないと社会全体には広がりませんからね……。
- 山﨑:
- 私たちはよく「社会実装」という言葉を使うのですが、世の中のためになるものは、多くの場面で利用できるようにする必要があります。有用な化学的反応がどのように起こるのか。どうしたら使えるようになるのか。こうしたメカニズムを解き明かせば、未利用の鉱物の中から適した原料を見つけ出せるかもしれない。エンジニアリング、つまり工学の力が求められるわけですね。
ひとつの課題から生まれた
イノベーション
「こんなことができたら」。社会課題とビジネスチャンスへの気付きから、日本国土開発と山﨑教授とのコラボレーションが始まりました。環境汚染物質の処理に新たな可能性をもたらした素材開発とは。
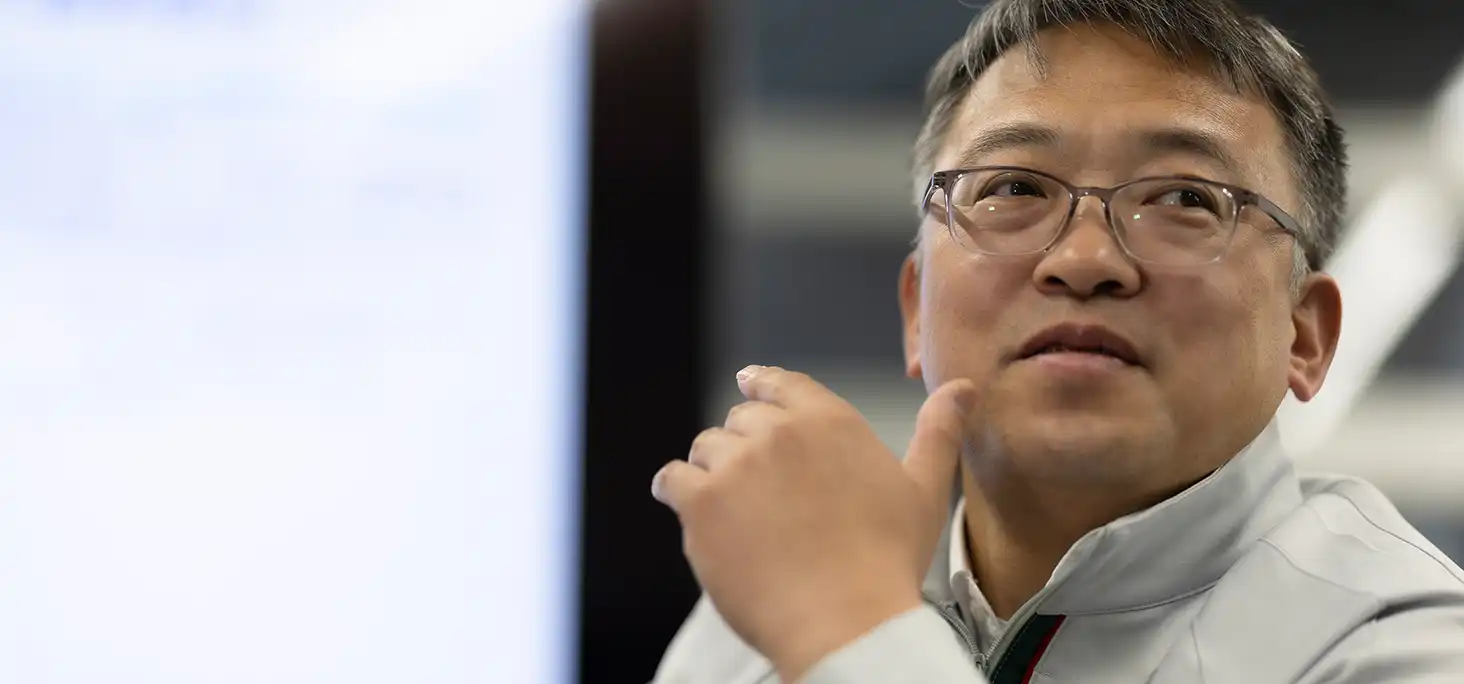
- 劉:
- かれこれ10年以上前になりますが、私が日本国土開発に入社するきっかけになったのが、山﨑先生と当社で共同研究していた素材、「NLDH®」だったんです。
- 山﨑:
- 研究の始まりは、日本国土開発の方から「マイナスイオンを安く、実用的に吸着できる素材をつくりたい」とお話をいただいたことでした。工場跡地の開発などをはじめ、建設では汚染物質を適切に処理しなくてはならない場面が多く存在します。
これまでも、鉛、カドミウム、水銀といった「プラスイオン」を吸着できる安価な素材は存在していました。一方で、ホウ素、フッ素、六価クロム、ヒ素、セレンなど「マイナスイオン」を、低コストで吸着できるものは存在しなかったのですね。
- 劉:
- プラスイオンを吸着できる素材は粘土をはじめとしていろいろとありますが、マイナスイオンを吸着するのはイオン交換樹脂とか、キレート剤とか、高い材料しかありませんからね。「社会実装」が難しかったのですよね。

- 山﨑:
- これを低コストで処理できるようになれば、環境分野でのビジネスチャンスが生まれるのではないかと。
- 劉:
- 最初の展示会でクロムの排水を用意したんです。黄色い色のついた排水が、NLDH®の中を通過して、透明の水になって出てくる。これはわかりやすかったし、みんな驚いてくれました。
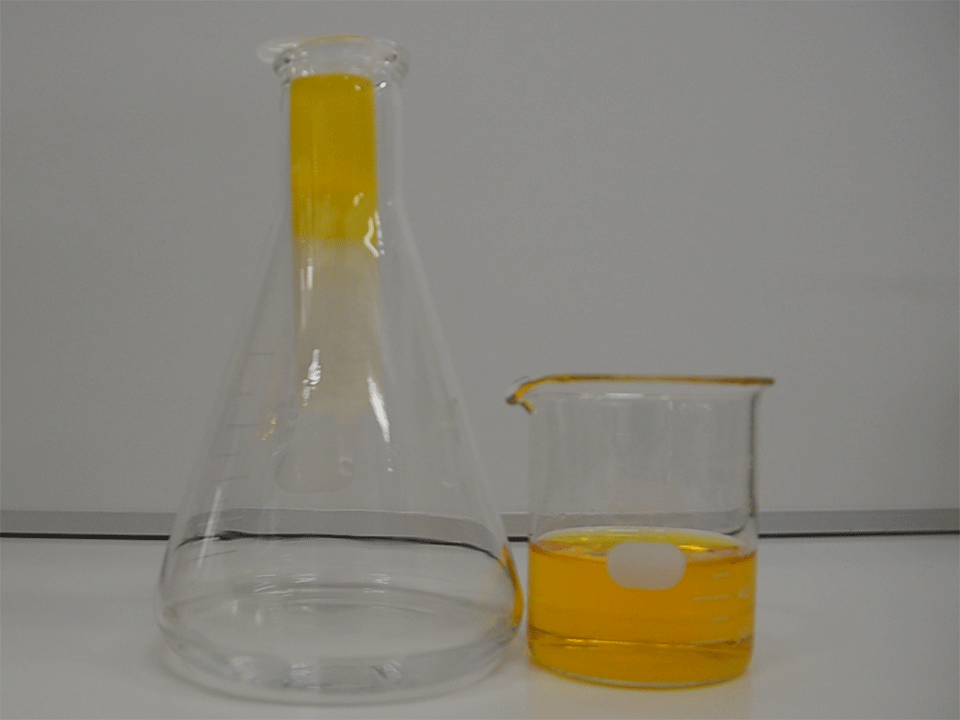
- 山﨑:
- 日本国土開発さんに、初めて実験的に見せたときにも同じことをやったのを覚えています。六価クロムの黄色い溶液が無色になって「おおっ」みたいな。使えそうな鉱物については、そこそこ目星がついていました。世の中で知られている鉱物はだいたい6,000種類くらいで、ある程度それらの構造と性質がわかっていたので。
- 劉:
- 6,000種類。すごい。
- 山﨑:
- まあ、全部頭に入っているというのは言い過ぎかもしれませんが(笑)。それでも、「これなら行けるんじゃない?」というものが繋がるというか。「これ、できるの?」と聞かれて「できますよ!」とお伝えしたところから、研究が本格化していったわけですね。